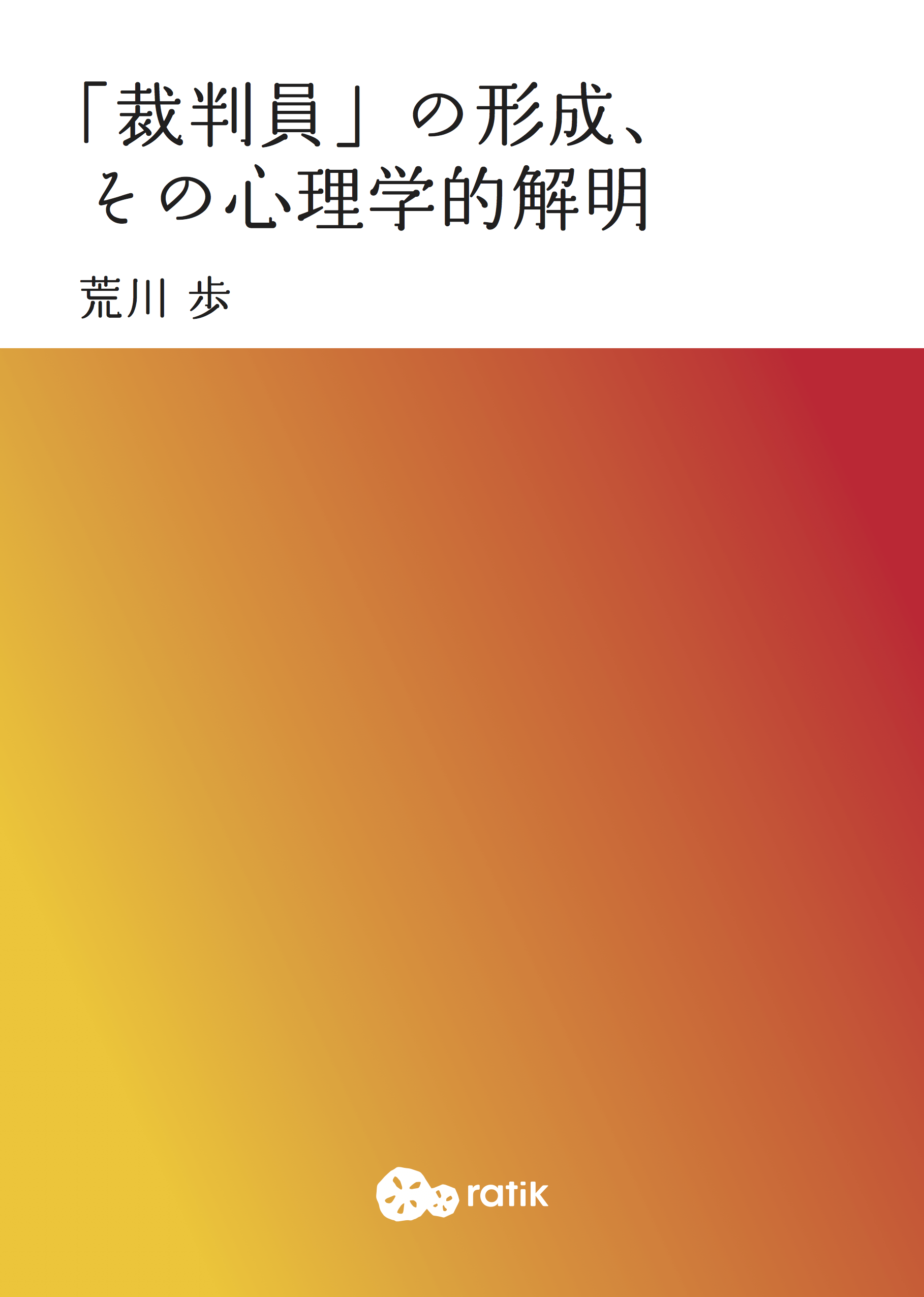

書名:「裁判員」の形成、その心理学的解明
著者:荒川 歩
(序言:菅原 郁夫(早稲田大学大学院法務研究科・教授))
発行年月:2014年4月1日(EPUB)
発行年月:2014年4月5日(PDF)
発行者:特定非営利活動法人ratik
ISBN:978-4-907438-00-5(EPUB)
ISBN:978-4-907438-04-3(PDF)
電子書籍ファイル形式:EPUB・リフロー、PDF
ファイル容量:10.3MB(EPUB)、33.0MB(PDF)
文字数:約145,000字
販売価格:2,500円(消費税込):電子書籍のみ
:3,800円(消費税込)電子書籍 + 印刷・製本サービス
◆ 電子書籍(EPUB版・PDF版)のみを購入する
(ご購入から書籍ダウンロードまでの手続きの詳細については「電子書籍のご購入について」「書籍ご購入までの流れ」をご覧ください。)
■「PayPal決済(各種クレジットカード利用可)」で書籍をご購入の場合は、下の青色ボタンをクリックして「カート」に商品を入れ、手続きをお進めください。
(ご購入いただくとEPUB/PDFの2つのバージョンをダウンロードしていただけます。)
■「ゆうちょ銀行振替口座への送金(振替・振込)」で書籍をご購入の場合は、下の桃色ボタンをクリックして「注文フォーム」にお進みください。
(ご購入いただくとEPUB/PDFの2つのバージョンをダウンロードしていただけます。)
¥2,500 − 銀行送金で購入
*EPUB版をご利用の際には、まずは「電子書籍の読み方」をご参照いただき、お客様の「電子書籍の閲覧環境」をお整えになった上で、「試し読み」「ご購入手続き」をお始めください。
*書籍の購入から、決済手続後のダウンロード、さらには各機器での閲覧まで、ご不明な点がありましたら、こちらからお問い合わせください。
■「試し読み用」の「無料」の「書籍サンプル・ファイル」を用意しました。お手持ちの機器・リーダーの動作確認を含めて、お試しください。下のボタンをクリックすることでファイルのダウンロードが始まります。
*本書・本文中には、細密なものも含めて多数の「図表」が含まれます。文中の画像を拡大できる機能を有したリーディング・システムで閲覧していただくことをおすすめします。
【パソコンの場合】calibre、Readium、EPUBreaderなど
【タブレット、スマートフォン】iBooks、Kinoppy、koboなど
◆ 「印刷・製本サービス付」で電子書籍を購入する
■電子書籍に加え「印刷・製本サービス」を利用して冊子体・書籍を入手される場合には、下の緑色ボタンをクリックして「注文フォーム」にお進みください。
¥3,800 – 印刷・製本サービス付で電子書籍を購入
- ご購入いただくとEPUB/PDFの2つのバージョンの電子書籍ダウンロードしていただけるほか、並製本の冊子体・書籍1冊(A5判・188頁)をお届けします。
- 印刷・製本サービス版はモノクロ印刷となります。本文中に幾つか含まれるカラー図表内の詳細につきましては、電子版にてご確認いただくこと、ご容赦ください。
- 代金のお支払いには「PayPal決済(各種クレジットカード利用可)」、「ゆうちょ銀行振替口座への送金(振替・振込)」をご利用いただけます。
- ご入金確認後、電子書籍ダウンロード用URLを発行し、冊子体・書籍の制作を開始しますので、書籍到着は、上記、電子書籍のみでご購入される場合に比べ遅くなります(冊子体発送まで1週間以上のお時間をいただく場合があること、ご容赦ください)。
- ratikの「印刷・製本サービス」に関する詳細は、こちらをご覧ください。
【バージョン情報】
■最新バージョン:ver1.1(2018年7月4日発行)
(お手持ちの書籍のバージョンは〈奥付〉ページでご確認ください。)
■変更内容
【EPUB ver1.0→ver1.1(2018年7月4日発行)】
2-3-2 証人に対するしろうと理論 第1段落の中程
(誤)
Lofus(1974)
(正)
Loftus(1974)
また、この文献に対応する書誌情報を巻末・引用リストに追加しました。
【PDF ver1.0→ver1.1(2018年7月4日発行)】
「印刷・製本サービス」の開始に伴い、組版をブラッシュアップしました。
また、2-3-2 証人に対するしろうと理論 第1段落の中程
(誤)
Lofus(1974)
(正)
Loftus(1974)
さらに、この文献に対応する書誌情報を巻末・引用リストに追加しました。
巻頭、早稲田大学大学院法務研究科・教授の菅原郁夫先生に非常に明晰な本書・解説をご寄稿いただきました。
…本書の特色は、裁判員を固定的な存在としてとらえるのではなく、動態的なものとしてとらえる点にある。すなわち、「市民=裁判員」ではなく、市民が一定の役割と環境のもと、市民から裁判員になっていくというのが本書の視点である。
そのような視点から見たとき、その過程に関わる心理学的要素は多く、かつ多面的である。また、固定化された特性ではなく、その変化に着目する分、本書では、裁判員に対する一面的な批判や消極論ではなく、中立的、科学的な視点から分析が導き出されている。(中略)
これまで、法と心理学の研究は、法律学者と心理学者がそれぞれの領域に立ち、対岸の他者を観察し、批判するといった内容のものが多かったように思う。本書はそれらとは一線を画し、「裁判員制度」という両方の領域にまたがる橋を架け、互いの領域に踏み込んだ考察をなすものである。記述は、著者の性格を反映してか、断言を避けた控えめなものが多いが、その分、議論の展開可能性を暗示させるものがある。本書が、裁判員研究の新たな地平を切り開くことを大いに期待する。
菅原 郁夫(早稲田大学大学院法務研究科・教授)本書「序言」より抜粋
【目次】
序言 裁判員になるという視点(菅原 郁夫)
はじめに
第1章 「裁判員」という役割
- 1-1 裁判員と裁判官の違い
- 1-2 市民がもつ事象・法的概念のイメージ:常識にもとづく法
- 1-3 裁判員=市民ではない
第2章 公判における「裁判員」の形成
- 2-1 裁判員は公判の中でどのように心証を形成するか
- 2-2 事実認定者としての裁判員の限界
- 2-3 心理的事象に対する市民の理解と専門的知識のズレ
- 2-4 弁論の内容が裁判員の意見形成に与える影響
第3章 評議における「裁判員」の形成
- 3-1 評議における裁判員の判断形成
- 3-2 評議の運営が裁判員の判断形成に与える影響
- 3-3 実際の裁判官が参加した模擬裁判と裁判員の満足
- 3-4 意見のズレの解消過程の分析と評議後の「裁判員」の判断の変化
第4章 まとめ
- 4-1 裁判員の心理はどのようなものと言えるか
- 4-2 本研究の限界
- 4-3 裁判員研究の意味
〈引用文献〉
〈謝 辞〉
〈著者紹介〉
【著者紹介】
荒川 歩(あらかわ あゆむ)
武蔵野美術大学 教養文化研究室 准教授
博士(心理学)
1976年大阪府生まれ
同志社大学大学院文学研究科博士課程(後期課程)単位修得退学
立命館大学人間科学研究所研究支援者、
名古屋大学大学院法学研究科研究員、
名古屋大学大学院法学研究科特任講師を経て現職
近著に、
- 『〈境界〉の今をたどる——身体から世界へ・若手15人の視点』(共編著)東信堂、2009年
- 『考えるための心理学』(共著)武蔵野美術大学出版局、2012年
- 『心理学史』(共編著)学文堂、2012年 など
制作の過程で、著者の荒川 歩さんから、本書の根底にある問題意識として次のようなエピソードを聞きました。
模擬裁判直後のアンケートで,多くの裁判員が模擬裁判の評議に満足したかという問いで「十分できた」に○をしているのに対し、その参加者だけは、5段階の満足度の下から2番目、満足できなかったことをしめすところに○をつけていた。
モニターを通して評議の内容を客観的に見ていた限り、裁判長は誠実に、できるだけ裁判員の意見を丁寧に聞き、自分の意見は最後まで言わないようにしているように見えた。いったいここで起こっているのはどのようなコミュニケーションなのだろうか。
本書は、裁判員裁判のプロセスの中で、人が裁判員に「なる」心理的過程を丹念に追いかけたものです。
「裁判員」という役割を担おうとするとき、人は或る種の期待に応え、その役割を果たそう・演じようとします。さらに、「プレーヤー」とでも呼べばよいのでしょうか、裁判員裁判には、専門家/非専門家といった区分に留まらず、種々の異なるバックグラウンドを背負った人物が参与します。
本書が基づいているのは、裁判員裁判という「グループ・ダイナミズム」の中で、種々の局面において「裁判員の意思」がどのようなプロセスを経て形成されていくのかを明らかにする研究であるとも言えるでしょう。
また、こうした研究は「心理学」全体のパースペクティヴから眺めた場合、単に裁判員裁判という限定された場面のみならず、人が、ある判断基準をもった集団に入り、その基準を学び、集団的な意思決定を行なうときの心理一般の解明に資するものになっていく筈です。
先進国において、(裁判官を含め)人は、他者の心理や能力について誤った信念をもっていても、それに気付かないという事実を踏まえ、心理学を含む社会科学の知識や方法を積極的に司法に取り入れようとする動きが高まっています。しかし、日本では「法と心理学」の位置づけはまだまだ高いとは言えない現状があります。
現在、心理学研究者として教鞭を執る傍ら、荒川さんが「学生」として法学部で勉学を続けられていることを知り、感銘を受けました。「司法」の在り方を変えていくためには、その内部に入り、そこで通じる言葉を磨いていかねばならない…。
本書が「社会科学にもとづく司法」の実現に寄与することを願っています。〔ratik・木村 健〕
【詳細目次】
序言 裁判員になるという視点(菅原 郁夫)
はじめに
- 模擬裁判での裁判員の言葉から
- 裁判員という時間
- 社会科学にもとづく司法
- これまでの裁判員研究
- 裁判員の心理過程のうち、本書では扱わないこと
- 本書の目的
- 裁判員制度とは
- 本書の構成
第1章 「裁判員」という役割
- 1-1 裁判員と裁判官の違い
- 1-1-1 裁判官と裁判員が受けている訓練や経験による思考の違い
- a) ストーリーモデル
- b) ストーリーモデルと性格
- c) ヒューリスティック
- d) ヒューリスティックと裁判官
- 1-1-2 裁判官と裁判員の文脈の違い
- 1-1-3 裁判官と裁判員では判断に違いがあるか
- 1-2 市民がもつ事象・法的概念のイメージ:常識にもとづく法
- 1-2-1 常識にもとづく法とは
- 1-2-2 市民は法的概念をどのように理解しているか
- 1-2-3 市民は心神喪失をどう捉えているか
- 1-2-4 法律や精神障害に対する知識の付与は市民の態度を変えるか
- 1-2-5 市民が事前にもつ態度や法律のイメージと裁判員制度
- 1-3 裁判員=市民ではない
- 1-3-1 裁判員になることの意味
- 1-3-2 裁判員のイメージとイメージによる負担感の違い
- 1-3-3 裁判員の役割に対する説明が事件に対する判断に与える影響
- 1-3-4 裁判員への基準の説明のタイミングが事件に対する判断に与える影響
第2章 公判における「裁判員」の形成
- 2-1 裁判員は公判の中でどのように心証を形成するか
- 2-2 事実認定者としての裁判員の限界
- 2-2-1 知覚・認知過程における歪み
- a) 知覚能力の限界
- b) 認知能力の限界
- c) 知覚・認知の特性
- 2-2-2 記憶過程における歪み
- a) 感覚記憶、作業記憶、長期記憶
- b) 系列位置効果
- c) 記憶の忘却
- d) 記憶の変容
- 2-2-3 判断過程における歪み
- a) 裁判員のバイアスと判断
- b) 裁判員の感情と判断
- c) 裁判員の属性と判断
- d) 裁判員の性格と判断
- e) 裁判員の態度と判断
- 2-3 心理的事象に対する市民の理解と専門的知識のズレ
- 2-3-1 公判における「しろうと理論」の影響
- 2-3-2 証人に対するしろうと理論
- 2-3-3 自白に対するしろうと理論
- 2-3-4 しろうと理論と専門家の理論を意識化する手段
- 2-4 弁論の内容が裁判員の意見形成に与える影響
- 2-4-1 裁判員に対する弁論の機能
- 2-4-2 裁判官役が殺意ありの心証をもつ殺人事件で弁護人の事前接種が与える影響
- 2-4-3 裁判官役が正当防衛ではないという心証をもつ殺人事件で 弁護人の事前接種が与える影響
- 2-4-4 弁論が裁判員に与える事前接種効果
第3章 評議における「裁判員」の形成
- 3-1 評議における裁判員の判断形成
- 3-1-1 評議における判断形成
- 3-1-2 集団意思決定における同調の影響
- 3-1-3 集団意思決定における属性・性格の影響
- 3-1-4 陪審の集団意思決定のモデル
- 3-1-5 裁判員裁判における専門家/非専門家コミュニケーションの理論
- 3-1-6 日本における裁判員評議のコミュニケーション分析
- 3-1-7 裁判員経験者の評議に対する感想
- 3-1-8 評議研究の課題
- 3-2 評議の運営が裁判員の判断形成に与える影響
- 3-3 実際の裁判官が参加した模擬裁判と裁判員の満足
- 3-3-1 実際の裁判官の裁判員模擬裁判を検討する意味と、評議に対する裁判員の満足を検討する意味
- 3-3-2 実際の評議におけるコミュニケーションの概要
- a) 発話の頻度・順序に関する分析
- b) 裁判長の役割
- c) 陪席裁判官の役割
- d) 裁判員の役割
- e) 評議のトピックの変遷
- f) 裁判員の意見の変遷
- g) 実際の評議におけるコミュニケーションのまとめ
- 3-3-3 判決、評議に対する満足に関する分析
- a) 事前・事後アンケートにおける目標・能力の認知と達成度
- b) 事後アンケートにおける満足度
- c) 事後インタビューにおける満足度
- 3-3-4 納得したポイントの分析
- a) 他の裁判員に対して「非常に納得」「納得」とされる場合
- b) 他の裁判員に対して「疑問」とされる場合
- c) 裁判長・裁判官に対して「非常に納得」「納得」とされる場合
- 3-3-5 実際の裁判官の裁判員模擬裁判研究のまとめ
- 3-4 意見のズレの解消過程の分析と評議後の「裁判員」の判断の変化
- 3-4-1 評議における意見のズレとその解消過程
- 3-4-2 時間をおいた後の裁判員の意見の変化
第4章 まとめ
- 4-1 裁判員の心理はどのようなものと言えるか
- 4-2 本研究の限界
- 4-3 裁判員研究の意味
- 4-3-1 実務に対する裁判員研究の意義と今後の展開
- 4-3-2 心理学研究に対する裁判員研究からの示唆と今後の展開
〈引用文献〉
〈謝 辞〉
〈著者紹介〉
