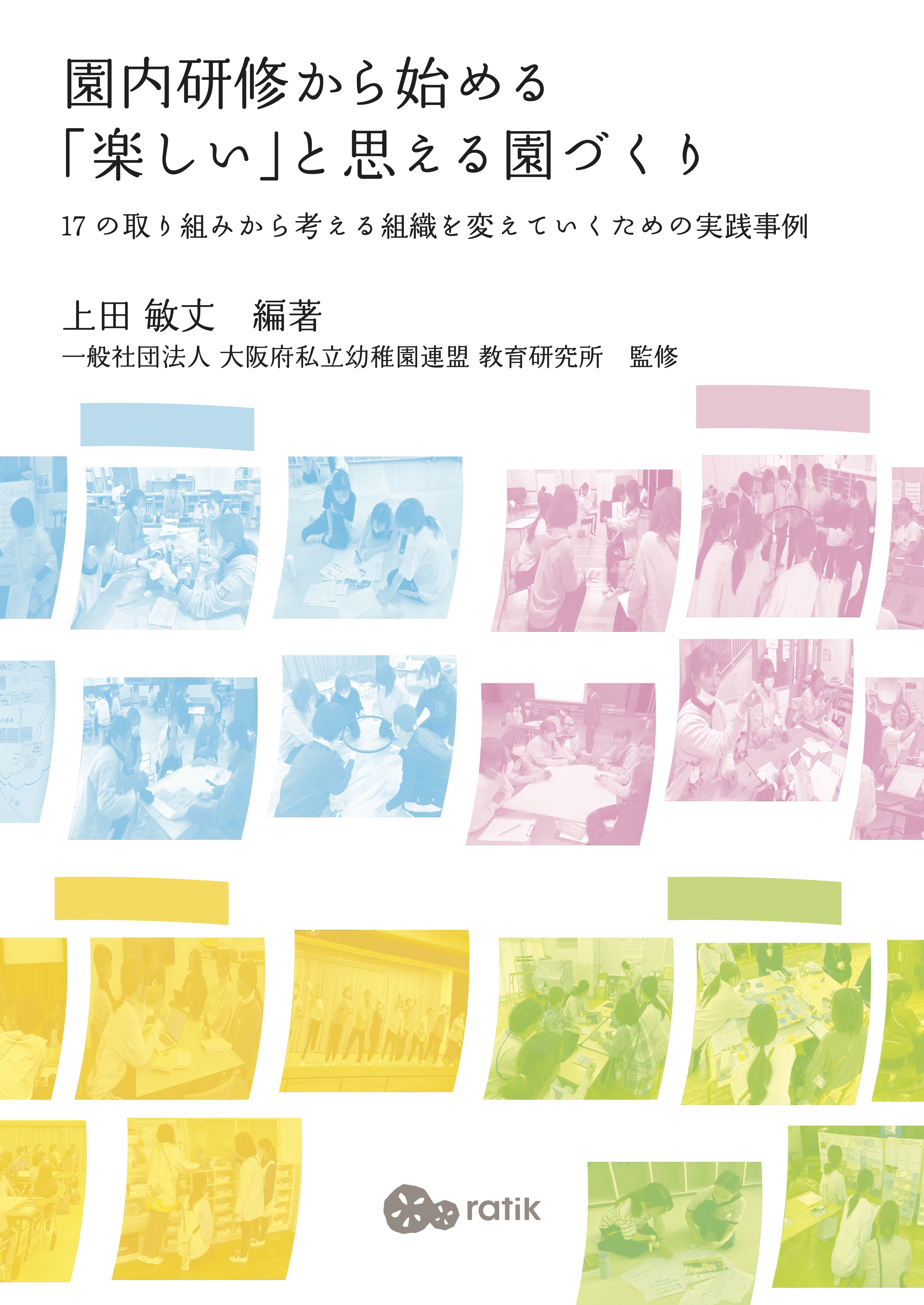

書名:園内研修から始める「楽しい」と思える園づくり:
17の取り組みから考える組織を変えていくための実践事例
著者:上田 敏丈 編著
一般社団法人 大阪府私立幼稚園連盟 教育研究所 監修
発行年月:2025年10月20日(EPUB・PDF)
発行者:特定非営利活動法人ratik
電子書籍ファイル形式:EPUB3.0・リフロー、PDF
ISBN:978-4-907438-70-8(EPUB)
ISBN:978-4-907438-71-5(PDF)
ファイル容量:108MB(EPUB)、108MB(PDF)
文字数:約12万字、写真、図版多数
カバーデザイン:POSTICS 溝口 賢
販売価格:1,500円(消費税込)電子書籍のみ
:3,000円(消費税込)電子書籍 + 印刷・製本サービス
◆ 電子書籍(EPUB版・PDF版)のみを購入する
(ご購入から書籍ダウンロードまでの手続きの詳細については「電子書籍のご購入について」「書籍ご購入までの流れ」をご覧ください。)
■「PayPal決済(各種クレジットカード利用可)」で書籍をご購入の場合は、下の青色ボタンをクリックして「カート」に商品を入れ、手続きをお進めください。
(ご購入いただくとEPUB/PDFの2つのバージョンをダウンロードしていただけます。)
■「ゆうちょ銀行振替口座への送金(振替・振込)」で書籍をご購入の場合は、下の桃色ボタンをクリックして「注文フォーム」にお進みください。
(ご購入いただくとEPUB/PDFの2つのバージョンをダウンロードしていただけます。)
¥1,500 − 電子書籍のみ、銀行送金で購入
*本書の「EPUB版」をご利用の際には、まずは「電子書籍の読み方」、「結局、何で読めば良いのか?」、「スマホで読むためのクイックマニュアル」などをご参照いただき、お客様の「電子書籍の閲覧環境」をお整えになった上で、「ご購入手続き」をお始めください。
*本書の「PDF版」は、1ページを「B5」サイズを想定して作成しています。「B4印刷」の際には、2アップが便利です。
*本書は数多くの写真画像を含む内容のため「EPUB版」「PDF版」ともに、かなり大きなファイル容量に仕上がっています。お求めの後、ダウンロード時などには、良好な通信環境を保持し、受け入れ機器の容量を確保しておいてくださることをお願いします。
*書籍の購入から、決済手続後のダウンロード、さらには各機器での閲覧まで、ご不明な点がありましたら、こちらからお問い合わせください。
◆ 「印刷・製本サービス付」で電子書籍を購入する
■電子書籍に加え「印刷・製本サービス」を利用して冊子体・書籍を入手される場合には、下の緑色ボタンをクリックして「注文フォーム」にお進みください。
¥3,000 – 印刷・製本サービス付で電子書籍を購入
- ご購入いただくとEPUB/PDFの2つのバージョンの電子書籍ダウンロードしていただけるほか、並製本の冊子体・書籍1冊(B5判・130頁)をお届けします。
- 印刷・製本サービス版はモノクロ印刷となります。本文中に含まれるカラー写真・図版等の画像は、電子版にてご確認いただくこと、ご容赦ください。
- 代金のお支払いには「PayPal決済(各種クレジットカード利用可)」、「ゆうちょ銀行振替口座への送金(振替・振込)」をご利用いただけます。
- ご入金確認後、メールにて電子書籍ダウンロード用URLをお知らせし、冊子体・書籍の制作を開始しますので、書籍到着は、上記、電子書籍のみでご購入される場合に比べ遅くなります(冊子体発送まで1週間以上のお時間をいただく場合があること、ご容赦ください)。
- ratikの「印刷・製本サービス」に関する詳細は、こちらをご覧ください。
【バージョン情報】
■最新バージョン:EPUB・PDF ver1.0(2025年10月20日発行)
(お手持ちの書籍のバージョンは〈奥付〉ページでご確認ください。)
子どもたちが、予測不可能な社会の中で生き抜く力を身につけていくために。
園内研修により組織としてのまとまりを生み出し、それが一人一人の保育者の力量を高め、保育の質向上に繋がっていく。園内研修を軸とした組織変化のプロセスの4つのフェーズの各段階にある、様々な園が、
- どのような課題を感じ、
- どのような工夫を凝らして研修を実施し、
- それが、どのように園の職員に受け止められ、
- 組織がどのように変わってきたのかを、
実際の保育現場で職員をまとめていく「ミドルリーダー」の視点からとりまとめる。
保育について話しあい、学び続ける組織に向けて。
【本書「はじめに」より】
本著は、一般社団法人 大阪府私立幼稚園連盟の教育研究所の2年間にわたる研究プロジェクトの成果を中心にまとめたものとなっています。当研究所、第31次プロジェクトでは「園内研修から始める組織開発」と題して、上田敏丈先生と連盟加盟園より申し込みをいただいた各園の先生方とともに実践研究を進めてきました。「組織開発」という言葉は、幼児教育・保育施設の中では積極的に使用されているものではないかもしれません。ただ、年々幼児教育・保育に関連する政策や動向は大きな変化を見せており、少子化が進む日本にあっても、施設類型によっては以前より職員数が増加したということもあるかと思います。
そのような中で、理事長や園長をはじめとするトップリーダーが方針や思いを伝え共有していくことも大切ですが、合わせて、職員集団がただ決められたことを決められたように行うだけではなく、各自が保育実践や業務に対して建設的な問いを持ち、その問いを互いに伝え合い討議できる、時間、空間、機会があることが大変重要となります。現代においては「働き方改革」なども進み、業務の精選、精査がなされていますが、その中でも「対話する時間」など人と人とがコミュニケーションをとる時間は、必要業務として上位に入るものではないでしょうか。
私たちはそのような「対話」、「コミュニケーション」の場について、今回のプロジェクトテーマにも包含した「園内研修」を手掛かりに考えていくことにしました。参加メンバーの中には、「私の園はまだ年間数回しか全体の園内研修ができていない」、「対話型ではなく講義型の園内研修が多い」、「園内研修はしているが、マンネリ化したり成長や変化を感じくい状況で困っている」など、各園様々なフェーズであることが当初の例会などで浮かび上がってきました。しかし、そのことが本実践研究を進めるにあたり大変意義深いことでありました。施設規模や園内研修のフェーズに応じてチームを編成し、それぞれの園で取り組んできたことを毎月の例会で共有し、その報告から共通点や、園ごとの差異等を見出し、各園、各自の問題意識に応じた園内研修の在り方、時間的な観点など、各園が持つ資源、状況、文脈をふまえてできる園内研修の在り方など、例会を中心とした研究で得た知識、考えなどをもとに、各園での実践をブラッシュアップすることにつながっていきました。結果として、各園がプロジェクトをスタートした時より、数歩先に歩んでいけたものと思います。
本著では、その園内研修を手掛かりにし組織について考えてきたプロセスや、その途中での葛藤や苦悩、難しさなども含めて保育現場の先生方ならではの視点で考えていただけるものになっていると思います。またそのプロセスや事例に対し、上田先生が包括的に理論的背景を交え、解説をいただいていることで、私たち幼児教育・保育施設が何に留意することが必要なのかについても明らかになってくるものと思います。
本著が読者の皆様にとって、「よし!やってみよう」と次への一歩を踏み出せる勇気を持っていただく一助となると幸甚です。
一般社団法人 大阪府私立幼稚園連盟 教育研究所 所長
幼稚園型認定こども園 高槻双葉幼稚園 園長
岡部 祐輝
【本書「おわりに」より】
「日々の保育へとつながっていく」
今、様々な園で園内研修が行われているかと思いますが、研修の形は様々で、どの園も試行錯誤の道程の途中かと思います。事例を提供してくださった17の園に共通していたのは、「子どもたちの育ちを支えるために、何とかしたい、少しでもいい方向に変えていきたい」という思いではないでしょうか。その思いから始まった園内研修の中には、すぐに効果が現れたものもあれば、効果がすぐには見えてこないものもあると思います。それでも、そのすべての取り組みが子どもへのまなざしに支えられた大切な歩みであることには変わりはありません。
保育の質の向上や園の組織改革にすぐに効く薬やサプリのようなものがあればいいなと思うこともありますが、魔法のような特効薬はありません。それよりも、日々の保育の中で感じる小さな違和感や課題に向き合い、立ち向かうための「体力」を養うことが大切ではないでしょうか。その意味で、園内研修はまさに継続的なトレーニングのようなものだと思います。時間はかかっても、子ども理解が深まり、同僚性が育まれ、保育の質が少しずつ高まっていく──そんな姿を思い描いています。
園内研修は、一度きりではなく、日々の気づきや問いに寄り添いながら継続していくものです。「保育の面白さを実感することが、より良い園づくりにつながる」という上田先生の「物語的保育論」にふれたとき、園内研修もまた、日々の保育者同士の語り合いの延長にあるのだと感じました。また上田先生は「保育の場は保育者と幼児の関係性の中で作りあげられる」とも語っておられます。その関係性から明日の保育が生まれるように、園内研修も保育実践とつながりながら、気軽に、楽しく続けられるものであってほしいと思います。そしてその積み重ねが、ゆっくりと園そのものを育てていくことを願っています。
一般社団法人 大阪府私立幼稚園連盟 教育研究所 副所長
せんりひじり幼稚園・ひじりにじいろ保育園 副園長
安達 かえで
【目 次】
はじめに:第31次プロジェクト
- 【理事長 挨拶】
- 【所長 挨拶】
第1章 理論編 園内研修から保育の「実感」へ
- 1節 はじめに
- 2節 これからもとめられる就学前施設での子どもの育ち
- 1項 VUCA時代に求められる乳幼児期の育ち
- 2項 日本の学校教育の転換
- 3項 これからの就学前教育の在り方
- 3節 園内研修の役割
- 1項 園内研修とは
- 2項 園内研修における学び
- 3項 保育を話しあう園内研修
- 4節 園内研修を組織の育ちにつなげる
- 1項 学び続ける組織
- 2項 組織開発という考え方
- 5節 実践編にむけて:大阪府の私立幼稚園との2年間の取り組み
- 1項 31次プロジェクト活動の内容
- 2項 取り組みのプロセス
- 3項 園内研修から始める組織開発としての4つのフェーズ
- 6節 本書について
第2章 実践編:研修をやっていこう
- 保育や子どものことについて個人の思いをどうやってみんなに発信すればいい?
- 先生同士が相談しやすい職員関係を作るにはどうしたらいい?
- 子ども理解や子どもの育ちを共有する研修はどうやって始めたらいいの?
- 子ども理解? 子どもの姿とは?? 子どもの興味関心を深めるためには??
- 明日の保育が楽しみになるには?
第3章 実践編:研修リーダーシップをとっていこう
- ふだん聞けない疑問や保育の悩みを気軽に聞けるようにするためには?
- 補助教職員がチームの一員として積極的に保育に入り、子どもと関わるには?
- 自分たちで環境構成を変えていくようになるためには?
- ミドルが主体になってしまわないためには?
第4章 実践編:研修の価値をあげていこう
- いくら研修をしても職員間の信頼関係がないと本音では話せない!
- 担任の先生達にとって研修が自分事になっていないのでは?
- お互いの保育観がわからない!
- 隣のクラスがどんな保育をしているのかわかっていない!?
- 「子どもの育ちの語りあい」「職員間の話し合い」は大切!! でも…事務時間の確保や様々な働き方の職員がいる中で特に勤務時間外の夜に行う研修が職員の負担になっている?
- 障がい児保育を通して、臨床心理士と共に保育士が主体的に意見を交わし保育の方向性を見出していく
第5章 実践編:研修で学び続けていこう
- 学年を超えて子ども達の姿が共有でき、教育課程と子どもの姿をつなげ
- 行事を通して子ども一人一人が主役になる
おわりに
- 【担当副所長 おわりに】
- 【副所長 コメント】
著者紹介
【著者紹介】
上田 敏丈(うえだ はるとも)
編著・第1章
名古屋市立大学 大学院人間文化研究科 人間の成長と発達分野(社会と教育) 教授
博士(教育学、広島大学)
研究キーワードは、幼児教育学、保育学、質的研究、保育者養成
濱本 歩美(はまもと あゆみ)
第2章 1節 担当
幼保連携型認定こども園 ひじり幼稚園・ひじり保育園
吉田 由紀子(よしだ ゆきこ)
第2章 2節 担当
白鳩幼稚園
喜多條 聡子(きたじょう さとこ)
第2章 3節 担当
平和幼稚園
渡邊 渚(わたなべ なぎさ)
第2章 4節 担当
幼稚園型認定こども園 朋来幼稚園
長﨑 元気(ながさき げんき)
第2章 5節 担当
幼保連携型認定こども園 みゆき西こども園
堀 季美(ほり すえみ)
第3章 1節 担当
幼保連携型認定こども園 金田幼稚園
藤本 真知子(ふじもと まちこ)
第3章 2節 担当
幼稚園型認定こども園 東豊中幼稚園
澤 結香(さわ ゆか)
第3章 3節 担当
幼保連携型認定こども園 関目聖マリア幼稚園
木村 弥生(きむら やよい)
第3章 4節 担当
大阪商業大学附属幼稚園
染矢 志保(そめや しほ)
第4章 1節 担当
光の園幼稚園
楠田 華子(くすだ はなこ)
第4章 2節 担当
幼稚園型認定こども園 念法幼稚園
今井 明美(いまい あけみ)
第4章 3節 担当
幼稚園型認定こども園 みくにひじり幼稚園
加藤 貴幸(かとう たかゆき)
第4章 4節 担当
幼保連携型認定こども園 熊野田幼稚園
塩塚 ひとみ(しおづか ひとみ)
第4章 5節 担当
幼保連携型認定こども園 庄内こどもの杜幼稚園
<事例内の当事者のプライバシーに配慮し、匿名での報告
第4章 6節
大阪府内 某 幼稚園
米田 亜里沙(よねだ ありさ)
第5章 1節 担当
幼保連携型認定こども園 せんりひじり幼稚園・ひじりにじいろ保育園
吉岡 美香(よしおか みか)
第5章 2節 担当
幼稚園型認定こども園 高槻双葉幼稚園
本書POD(プリント オン デマンド)版は、Amazonでもご購入いただけるようにする予定です(Amazon経由でご購入いただく際には、電子書籍は入手していただけません)。しばらくお待ちください。
