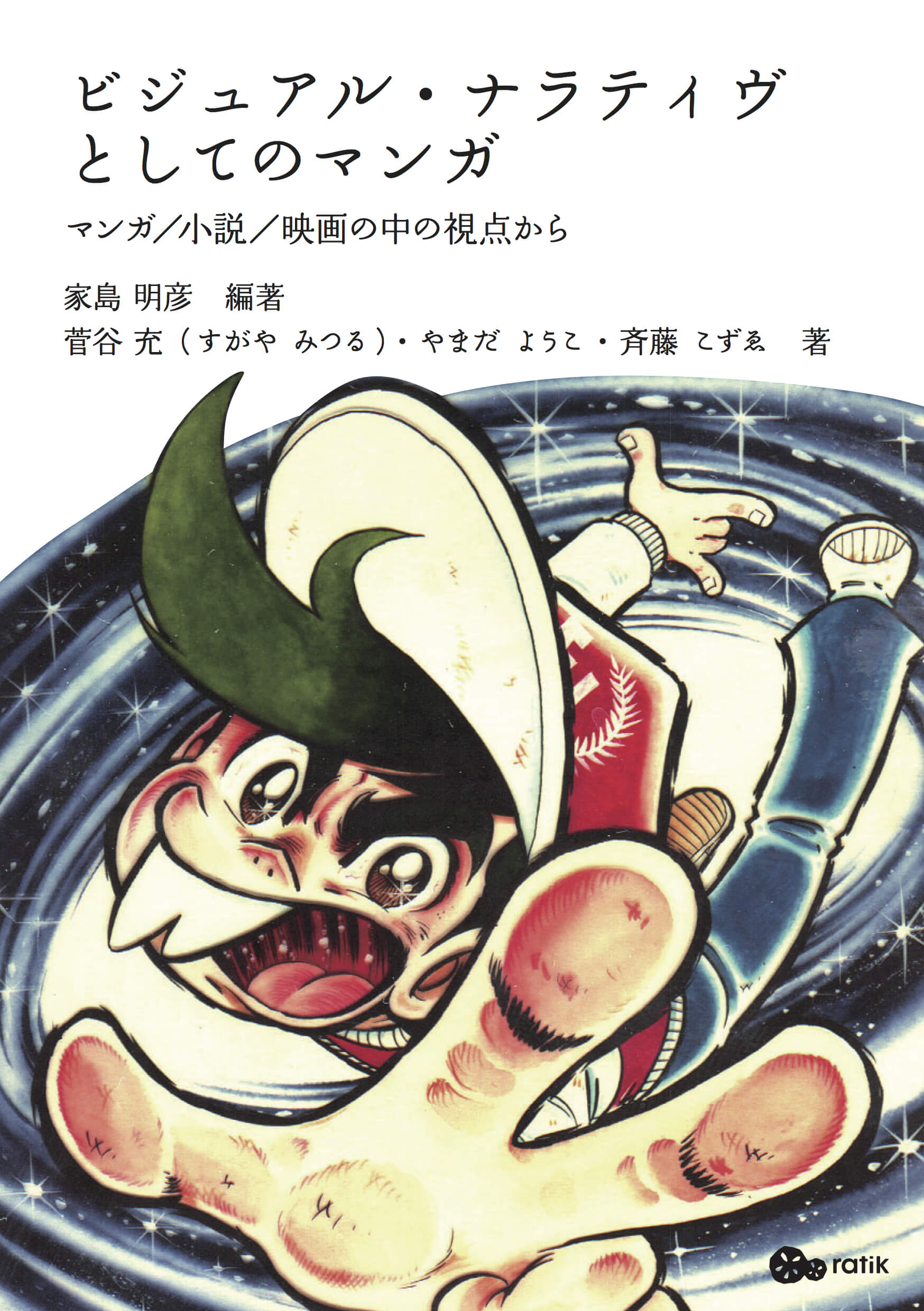

書名:ビジュアル・ナラティヴとしてのマンガ:マンガ/小説/映画の中の視点から
著者:家島 明彦 編著
菅谷 充(すがや みつる)
やまだ ようこ
斉藤 こずゑ 著
発行年月:2015年9月11日(EPUB・PDF)
発行者:特定非営利活動法人ratik
ISBN:978-4-907438-14-2(EPUB)
ISBN:978-4-907438-15-9(PDF)
電子書籍ファイル形式:EPUB2.0.1・リフロー、PDF
ファイル容量:8.9MB(EPUB)、12.0MB(PDF)
文字数:約47,000字
販売価格:800円(消費税込)
(ご購入から書籍ダウンロードまでの手続きの詳細については「電子書籍のご購入について」「書籍ご購入までの流れ」をご覧ください。)
■「PayPal決済(各種クレジットカード利用可)」で書籍をご購入の場合は、下の青色ボタンをクリックして「カート」に商品を入れ、手続きをお進めください。
(ご購入いただくとEPUB/PDFの2つのバージョンをダウンロードしていただけます。)
■「ゆうちょ銀行振替口座への送金(振替・振込)」で書籍をご購入の場合は、下の桃色ボタンをクリックして「注文フォーム」にお進みください。
(ご購入いただくとEPUB/PDFの2つのバージョンをダウンロードしていただけます。)
¥800 − 銀行送金で購入
*本書の「EPUB版」をご利用の際には、まずは「電子書籍の読み方」、「結局、何で読めば良いのか?」、「スマホで読むためのクイックマニュアル」などをご参照いただき、お客様の「電子書籍の閲覧環境」をお整えになった上で、「試し読み」「ご購入手続き」をお始めください。
*本書の「PDF版」は、1ページを「A5」サイズを想定して作成しています。「A4印刷」の際には、2アップが便利です。
*書籍の購入から、決済手続後のダウンロード、さらには各機器での閲覧まで、ご不明な点がありましたら、こちらからお問い合わせください。
■「試し読み用」の「無料」の「書籍サンプル・ファイル」を用意しました。お手持ちの機器・リーダーの動作確認を含めて、お試しください。下のボタンをクリックすることでファイルのダウンロードが始まります。
【バージョン情報】
■最新バージョン:ver1.0(2015年9月11日発行)
(お手持ちの書籍のバージョンは〈奥付〉ページでご確認ください。)
■変更内容
「ビジュアル・ナラティヴ」という「新たな研究領域」へ!
一般に「ナラティヴ(物語・語り)」は、「経験の組織化や意味づけ方」と定義されます。狭義には、言語的に「語られたもの」や「語る行為」のみを表しますが、広義には「音楽」や「建築」などを含めて考えることが出来ます。
「ビジュアル・ナラティヴ」とは、「イメージ(画像・映像)」を伴う「視覚的なナラティヴ」のことを指します。現代日本で大衆に支持され、”Manga”として国際的にも影響力のある「マンガ」は、「経験の組織化や意味づけ方」という観点から、今日的に重要な「ナラティヴ」の1つです。また「文字」「絵」「コマ」で構成される「マンガ」は、「ビジュアル・ナラティヴ」の代表的なメディアといえるでしょう。
本書では「視点」をキーワードに、議論が展開していきます。それは、表現する者/表現を受け取る者にとって、「物をみる立場、観点」「どこから見ているのかというときの“どこ”」が重要な要素としてはたらくからです。マンガ、小説、映画というメディアの種類(特性・制約)によって異なる視点/共通する視点。作者の視点/読者の視点。さらに、非西洋の視点、子どもの視点、若者の視点など、様々な「視点」から「マンガ」の魅力に迫ります。
本書には「ビジュアル・ナラティヴ」の研究者にとって重要なエッセンスが詰まっています。また、物語を駆動し読者にページをめくらせる原動力としての「視線誘導」「謎の提示と解消」「敢えて見せない技法」の議論などからは、マンガを描く上での方法論として、表現者にとってのヒントが見つかるかもしれません。
なお、本書は日本発達心理学会第21回大会でのシンポジウムを元に構成しています。当日のライブ感を含め、改めて追加・整序された中身を味わってみてください。
〔本書「はじめに」からratik・木村 健が編成〕
【目 次】
1 はじめに(家島 明彦)
2 話題提供:マンガ/小説/映画の中の視点(菅谷 充)
3 指定討論:ことばを超えて(やまだ ようこ)
4 指定討論:映像で発達を追いながら(斉藤 こずゑ)
5 指定討論:表現、物語、キャラクター(家島 明彦)
6 指定討論に答えて(菅谷 充)
7 おわりに(家島 明彦)
【著者紹介】
家島 明彦
大阪大学教育学習支援センター講師
修士(教育学、京都大学)
認定心理士、キャリア・カウンセラー、ガイダンスカウンセラー
2003 年、大阪大学人間科学部人間科学科(教育心理学講座)卒業、2005 年、京都大学大学院教育学研究科修士課程(教育科学専攻教育方法学講座発達教育分野)修了、米国シカゴのノースイースタン・イリノイ大学(NortheasternIllinois University)心理学部Visiting Scholar(2007 年11 月~2008 年2月)を経て、2009 年、京都大学大学院教育学研究科博士課程(教育科学専攻教育方法学講座発達教育分野)学修認定退学。
島根大学教育開発センター助教、島根大学キャリアセンター講師(副センター長,キャリア教育部門長,就職支援部門長)などを経て、2014 年4 月より現職。
専門は、生涯発達心理学、キャリア教育。
菅谷 充(すがや みつる)
京都精華大学マンガ学部マンガ学科キャラクターデザインコース教授
漫画家、漫画原作者、小説家
1971 年、『仮面ライダー』(原作・石ノ森章太郎)でマンガ家デビュー。1983年、『ゲームセンターあらし』『こんにちはマイコン』の2 作で第28 回小学館漫画賞受賞。その後、大人向け学習マンガを多数執筆。
1994 年、『漆黒の独立航空隊』で娯楽小説作家としてデビュー。その後、架空戦記を中心に多数のノベルスを執筆。
著作は、マンガ、実用書、小説を合わせ200 冊以上。
2009 年、早稲田大学人間科学部eスクール卒業、2011 年、早稲田大学大学院人間科学研究科修士課程を修了後、早稲田大学人間科学部eスクールで教育コーチをつとめる。
2012 年、京都精華大学マンガ学部非常勤講師を経て、2013 年4 月より現職。
専門は、マンガ/教育工学(インストラクショナルデザイン)
やまだ ようこ
京都大学名誉教授、立命館大学衣笠総合研究機構教授(特別招聘研究教員)
博士(教育学、名古屋大学)
1970 年、名古屋大学文学部哲学科心理学専攻卒業、1976 年、名古屋大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程退学。
愛知淑徳短期大学講師、助教授、愛知淑徳大学助教授、教授、京都大学教育学部教授、京都大学大学院教育学研究科教授を歴任。2012 年、立命館大学衣笠総合研究機構生存学研究センター特別招聘教授を経て、2013 年4 月より現職。
専門は、生涯発達心理学、質的心理学、ナラティヴ心理学。
著書に『ことばの前のことば』『喪失の語り』『世代をむすぶ』(新曜社)、『私をつつむ母なるもの』(有斐閣)、編著書に『人生を物語る』(ミネルヴァ書房)、『質的心理学の方法』(新曜社)、Meaning in Action(Springer)、『人生と病いの語り』(東京大学出版会)、『この世とあの世のイメージ』(新曜社)など。
斉藤 こずゑ
國學院大學文学部教授
修士(教育学、東京大学)
1974 年、東京女子大学文理学部心理学科卒業、1981 年、東京大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程退学。
1981 年、國學院大學文学部専任講師、1984 年、國學院大學文学部助教授を経て、1991 年4 月より現職。
専門は、コミュニケーションの発達心理学、倫理の発達心理学、映像メディア・リテラシー研究。
【詳細目次】
1 はじめに
2 話題提供:マンガ/小説/映画の中の視点
- 2.1 マンガ家/小説家/研究者として
- 2.2 マンガを描く上での「視点」の扱い
- 2.3 問題意識の源流
- 2.4 読者にどのように見せるのか
- 2.5 視点とは何か
- 2.6 これは誰の視点で書かれたものか
- 2.7 文章における人称の重要性
- 2.8 人称と視点とは別
- 2.9 小説の視点記述を映像で表現すると
- 2.10 カメラは正直すぎるのか
- 2.11 ポリフォニーを難なく実現してしまうマンガ
- 2.12 落語におけるポリフォニー
- 2.13 視点の文学
- 2.14 これでいいのだ!
- 2.15 ラノベの時代の視点
- 2.16 マンガでわかる小説入門
- 2.17 撮影技術の進歩と、映画のなかの視点
- 2.18 エイゼンシュテイン・モンタージュ
- 2.19 マンガの視線誘導のルーツ
- 2.20 グリフィス・モンタージュ
- 2.21 脚本家の仕事/ディレクターの仕事
- 2.22 マルチカメラの弊害
- 2.23 小型軽量カメラの出現
- 2.24 カメラでなければ見えない映像
- 2.25 完成映像を想定しながら演技する
- 2.26 生身の人間の見えの実現
- 2.27 まったく新しい視点からの見え
- 2.28 映画の技法をマンガに活かす
- 2.29 どのようにしてマンガのページをめくらせるか
- 2.30 マンガを読む視線の動きを科学で解明する
- 2.31 マンガを描く際のメソッドを実証する
- 2.32 マンガにおける「引き」とは何か
- 2.33 「謎」の提示
- 2.34 左下・最後のコマに「謎」を仕込む
- 2.35 『漫画で億万長者になろう!』
- 2.36 「見せない」技法
- 2.37 一幕の芝居を客席から見るかのごとく
- 2.38 謎こそが物語を追い求めさせる
- 2.39 授業で4 コマ・マンガを描いてもらうと
- 2.40 自分を客観視する
- 2.41 「でも、めげないで頑張るぞ!」
- 2.42 マンガを描く理論の構築に向けて
3 指定討論:ことばを超えて
- 3.1 語りの研究
- 3.2 人生のイメージ地図
- 3.3 ビジュアル・ナラティヴ研究へ
- 3.4 ことばの制約を超えて表現できるもの
- 3.5 日本の伝統文化に依拠したビジュアル・ナラティヴ
- 3.6 西欧言語構造の枠組
- 3.7 視点の混乱と視点の自由
- 3.8 “I love you.” という枠組を疑う
- 3.9 ポリフォニーを日本文化からとらえると
- 3.10 自分でマンガを描くおもしろさ
- 3.11 作者/読者による物語の共同制作
4 指定討論:映像で発達を追いながら
- 4.1 自らもマンガ家を志した身として
- 4.2 子どもの発達を撮る
- 4.3 言語で表現するのと何が違うのか
- 4.4 子どもたちの視点/研究者の視点
- 4.5 手持ちの枠組みで表現すること
- 4.6 「私はこう思う」は主観的過ぎるのか?
- 4.7 体験と表現の相関
- 4.8 アンフェアであることが許されない記述
- 4.9 映像化で期待される新しい発達研究
5 指定討論:表現、物語、キャラクター
- 5.1 受け手の側の情報処理能力
- 5.2 多視点を想定しながら演じるベテラン俳優
- 5.3 表現から来るカタルシス/物語から来るカタルシス
- 5.4 キャラクターの力
6 指定討論に答えて
- 6.1 プロット重視の小説講座
- 6.2 連載継続とキャラクターの力
- 6.3 その場、その場で考える
- 6.4 語るな、描写せよ/描写するな、語れ
- 6.5 ポリフォニーをビジュアルに一挙に見せる
7 おわりに
〈著者紹介〉
