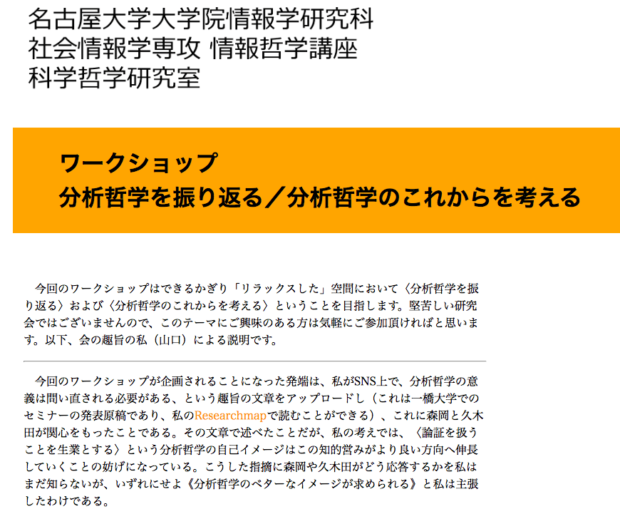〔ワークショップ開催案内のwebページより〕
4月6日に名古屋大学で開催された応用哲学会・大会のプレイベントであるワークショップ「分析哲学を振り返る/分析哲学のこれからを考える」を聴講してきました。
現代哲学の二大潮流とよばれる現象学と分析哲学のうち、現象学については(「事象そのものへ」というフッサールの当初の言葉とは裏腹に…)、思想史研究、文献学のようなスタイルが研究の主流になっている印象を私(ratik 木村 健)は以前から持っていました。事象自体が否応無く自分に突きつけてくる「問い」にではなく、歴史上著名な哲学者やその思想にのみ興味を示し、莫大な著作から「過去に誰が何を言ったのか」を綿密に読解・整理・再提示することこそが、現象学者のなすべき仕事とみなされているのではないか、という疑念と言い換えても良いかもしれません。
その意味で、主題そのものを、「それが何を意味するのか」「そのように述べる理由は何か」を明晰にしながら論じる分析哲学(…論じるものだと私が考えていた分析哲学)には、哲学本来の魅力のようなものを感じていました。しかし、今回のワークショップを聴講し、その分析哲学(界)にも既に思想史研究化、文献学化の潮流が押し寄せており、そうしたスタイルが今や主流となりつつあることが分かり、衝撃を受けました。
発表者の1人・山口 尚さんには2012年の大著『クオリアの哲学と知識論証』(春秋社)があります。この書籍の元になった博士論文のために採った準備・執筆戦略として、山口さんは「見通しのよい体系をもっている」分析哲学者としてデイヴィド・ルイスを引き合いに出し、次のようなスキーマを示しておられました。
- 学界で盛んに論じられているテーマの中で、ルイスも参戦しているテーマを選ぶ。
- そうしたテーマのうちで立場(イズム)の対立が分かりやすいものを選ぶ。
- そのテーマを論じる論文や書籍は手に入る限りすべて集める。
- 手に入った論著を時系列的にすべて読み、論戦の展開の骨組みを抽出する。
- 或る立場を自分の立場として選び、その立場にもとづく他の立場の論駁を組み立てる。
(山口さんの発表原稿より)
短期間のうちに整った「業績」を産出するために、このスキーマは有効なものだったと思われます。しかし、日本語で書かれた「分析哲学的な」本の中で「最も分析哲学的な」もののひとつとされる(←山口さん談)『クオリアの哲学と知識論証』が、こうした戦略で書かれたものであったことに、私は少なからぬショックを受けました。このやり方は、或る意味で、思想史研究化、文献学化してしまった現象学のスタンスに酷似しているからです。
山口さんご自身の中にも、上記のようなスキームで論考を書くことは「人生の無駄だ」「自分の実存的な成長にまったく寄与しない」という感覚が湧き上がり、試行錯誤の末、新たなスキームが採用されることになります。そして、この転向こそが、今回のワークショップ開催のベースになっているものなのです。
現在、山口さんの論文執筆スタイルは、下記のようなスキームに落ち着いているそうです。
- 自分にとって最も重要と思われる事柄を素直に書く。
- 事柄を立場(イズム)の差異や対立に帰着させることを避ける。
- 参考文献は、自分の言いたいことを言うのに必要な限りで取り上げる(網羅性や完備性を追求しない)。
- 楽しく読めるように工夫する(長い文章を読ませるレトリック上の工夫が必要)。
(山口さんの発表原稿より)
このワークショップは、分析哲学の営みがさらされている昨今の流れに「抗する」問題意識で企画されており、山口さんをはじめ、森岡正博さん・久木田水生さんらの発表では、現状への疑問と、自らが採ろうとしている方針が語られているように思いました(久木田さんの「ソクラテスのような哲学者が現代に生きていても、研究職のポストはない」という提起には考えさせられました…)。
もちろん、何らかの問いに取り組む時に、既に議論された事柄に目を配り、それらを明確に整理した上で、自説を展開する必要があるでしょう。また、現行の査読システムは、論文のクオリティを上げ、権威に寄らず優れた論文を「読まれるべきもの」として世に送り出す働きをしていることも確かでしょう。しかし、人の生に深く根ざした哲学の営みは、「過去に誰が何を言ったのか」を漏れなく網羅的に整理することから発するものではなく、むしろ、たとえ100-200年に一度であっとしても、これまで誰も問うてこなかった問いを「まずは問うこと」、これまでに誰も問題であることにすら気づいていなかった問いを「まずは問うこと」、から始まるのではないか、とも思われます。こうした考え方は、哲学に対する「ロマン(cf. 森岡さん)」(現代においては、もはやもたらされることのないロマン)に過ぎないのかもしれませんが…。
さらに今回、特に衝撃的だったのは、主にワークショップの登壇発表者よりもさらに若手の研究者から構成されたフロアからの意見の多くが、山口さんや森岡さんらの見解に対して、批判的・攻撃的であった(批判的・攻撃的であるように思えた)ことです。現状、研究職ポストがごく限られた日本の哲学界において若手研究者には、過去・同時代の他研究者の議論を綿密に整理し、その上で有名査読誌に採択されることが強く求められており、実際、教官からもそのような指導がなされていると聞きます。思想史研究的、文献学的な価値観を、あまりにも強く内面化した人々により、哲学コミュニティの多くが占められていくことには危機感を抱いてしまいます。
こうした現状を目のあたりにして、ratikとしては、哲学界に寄り添いつつも、どのような事業活動を行うべきか、しっかり検討していかねばなりません。